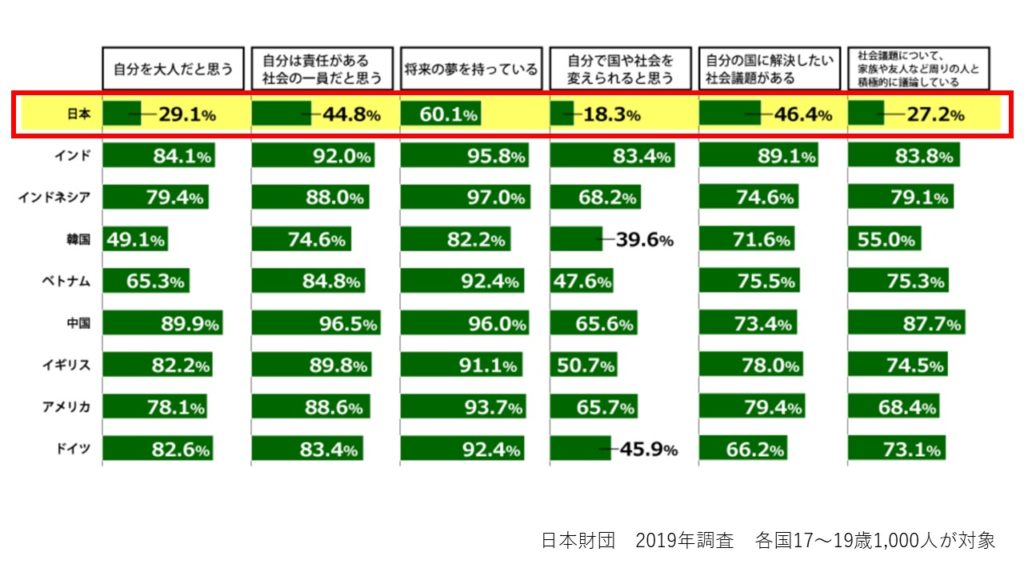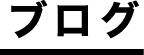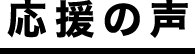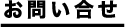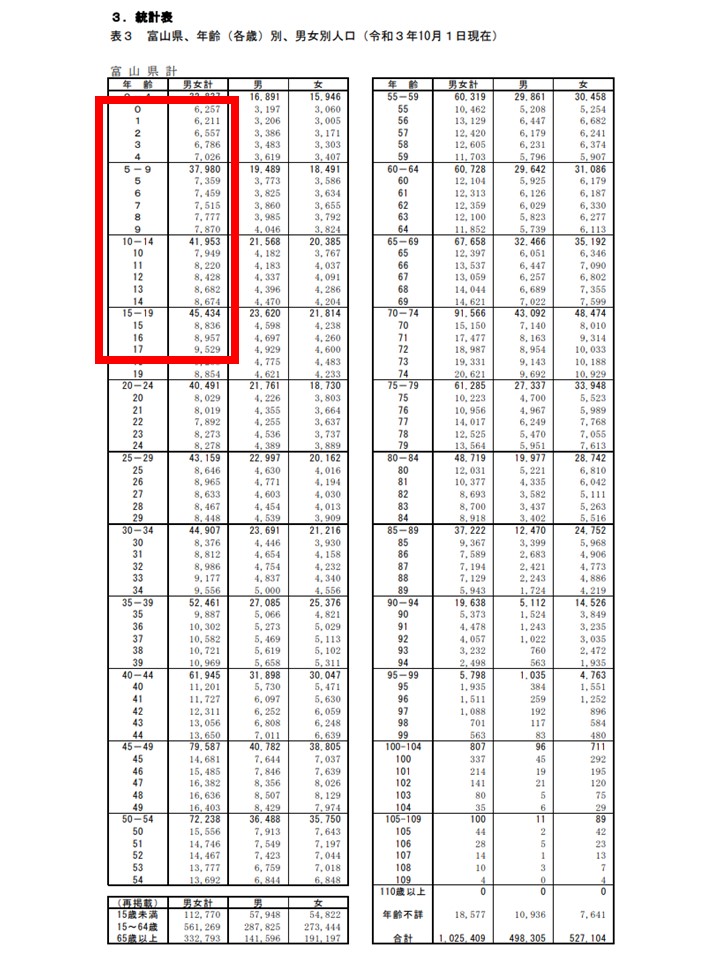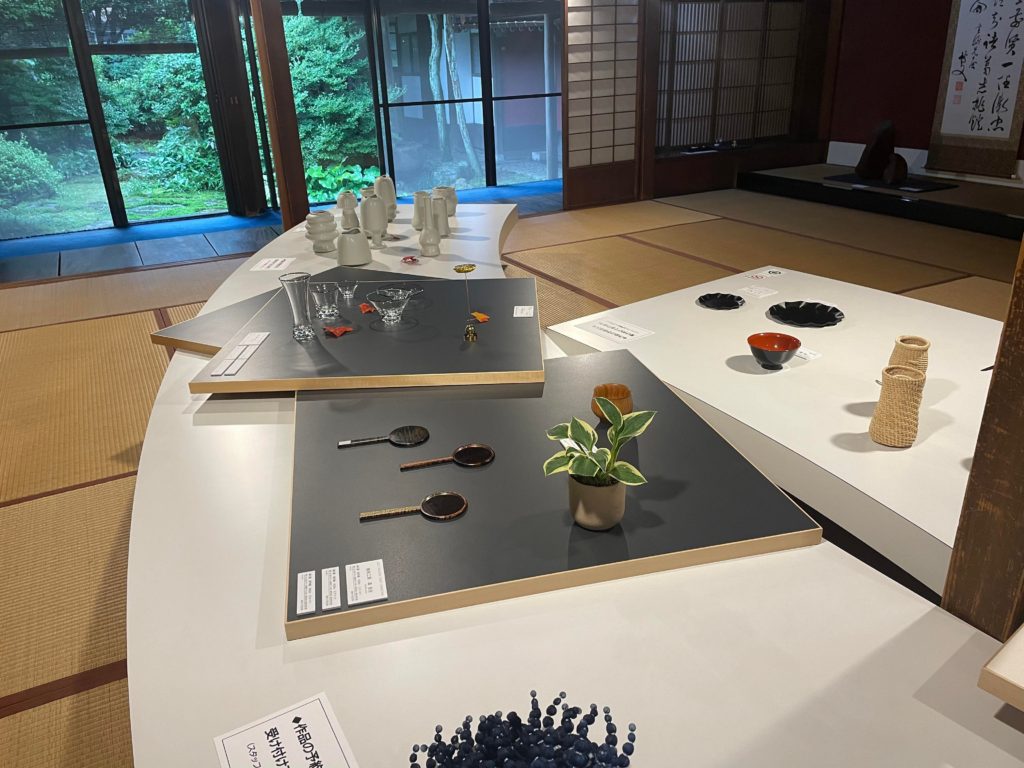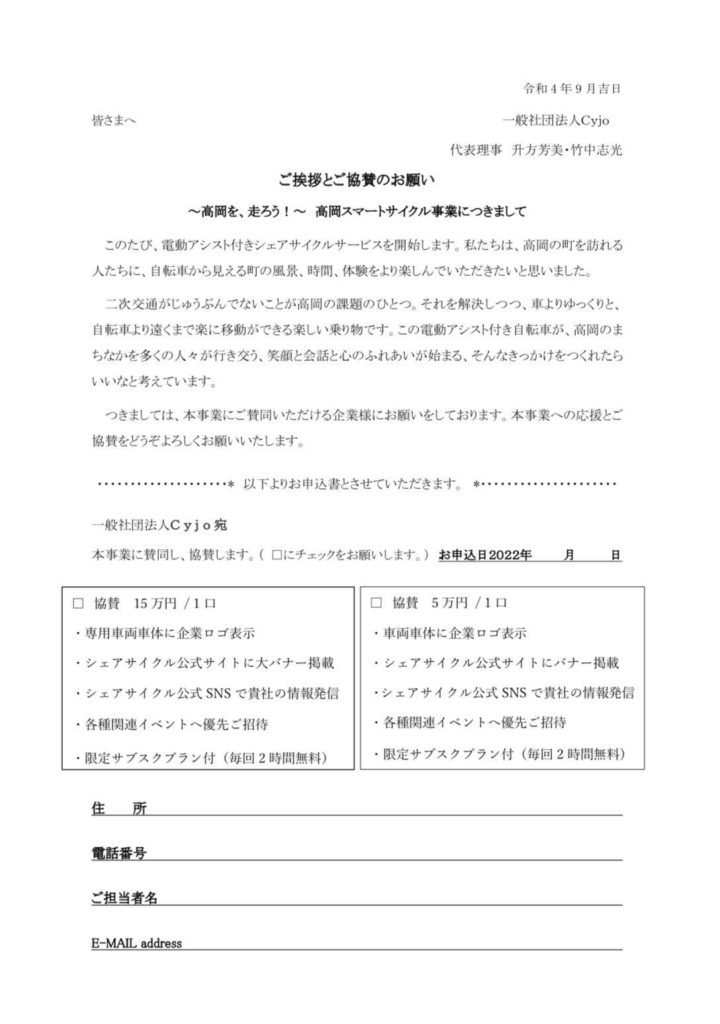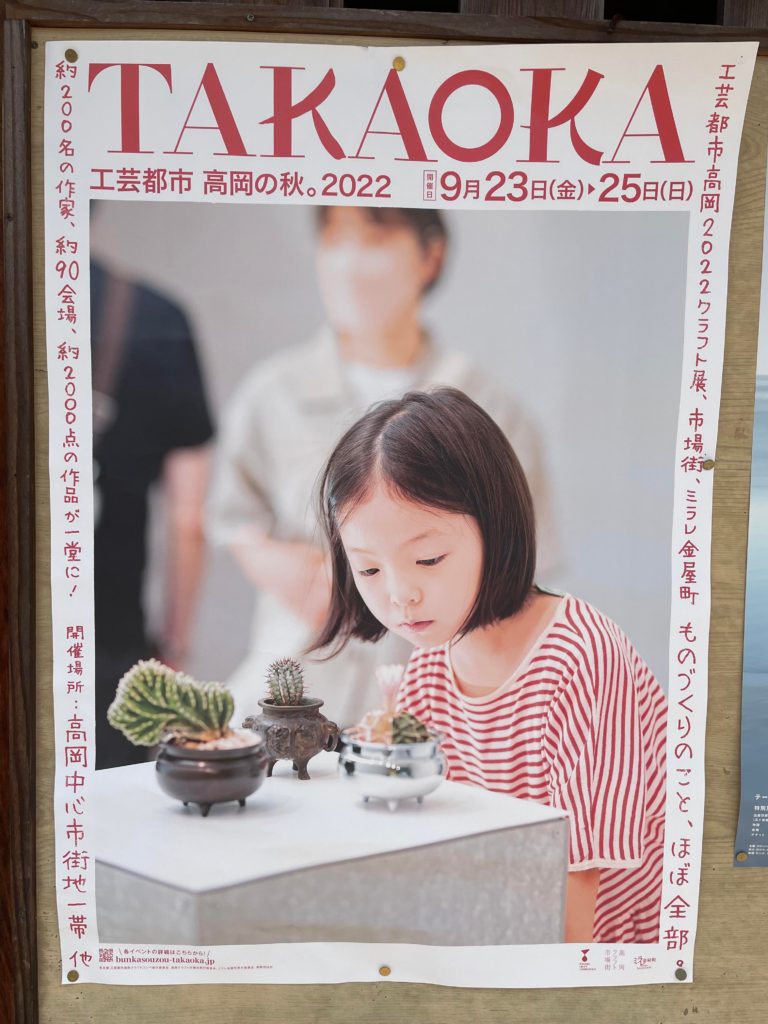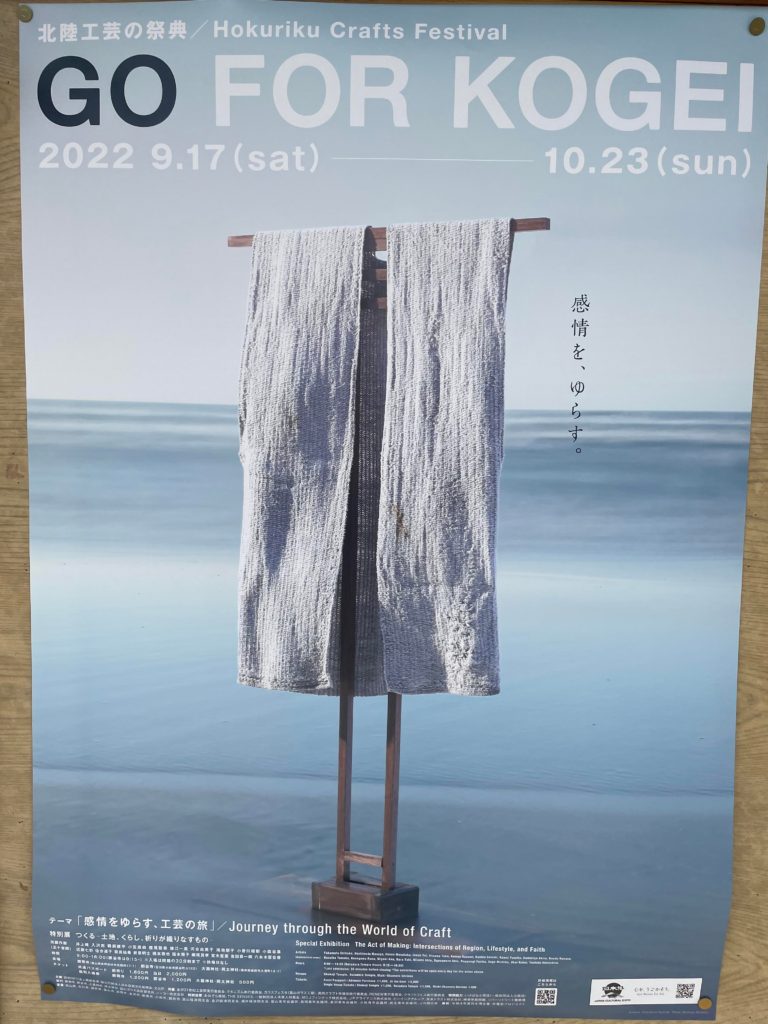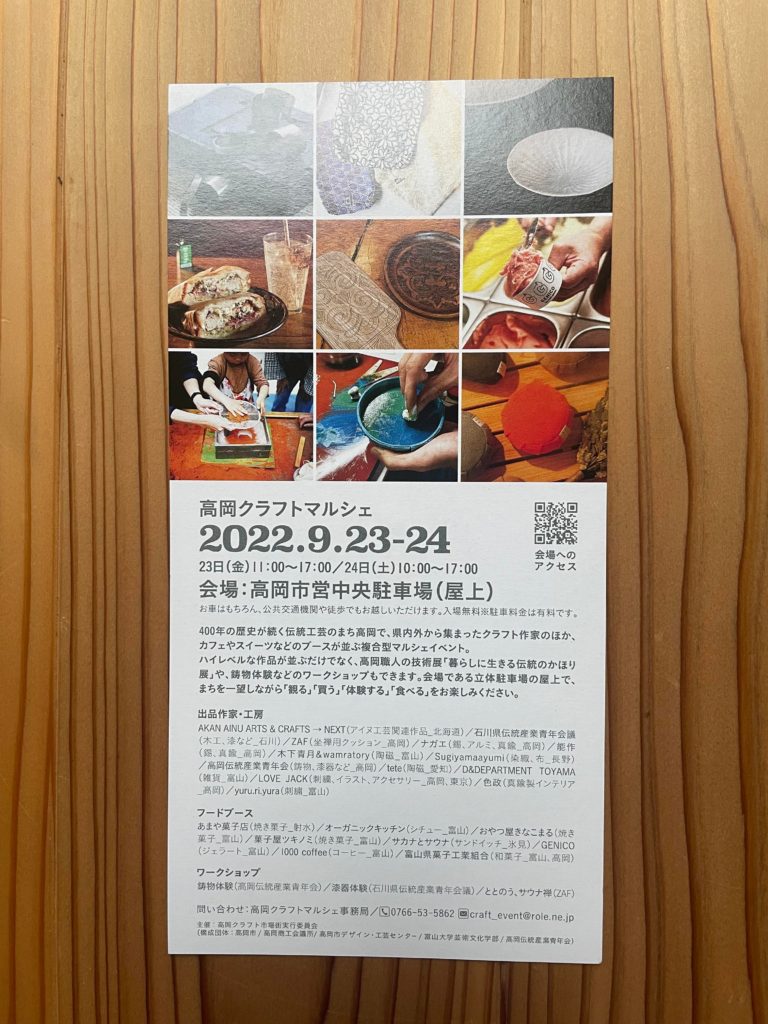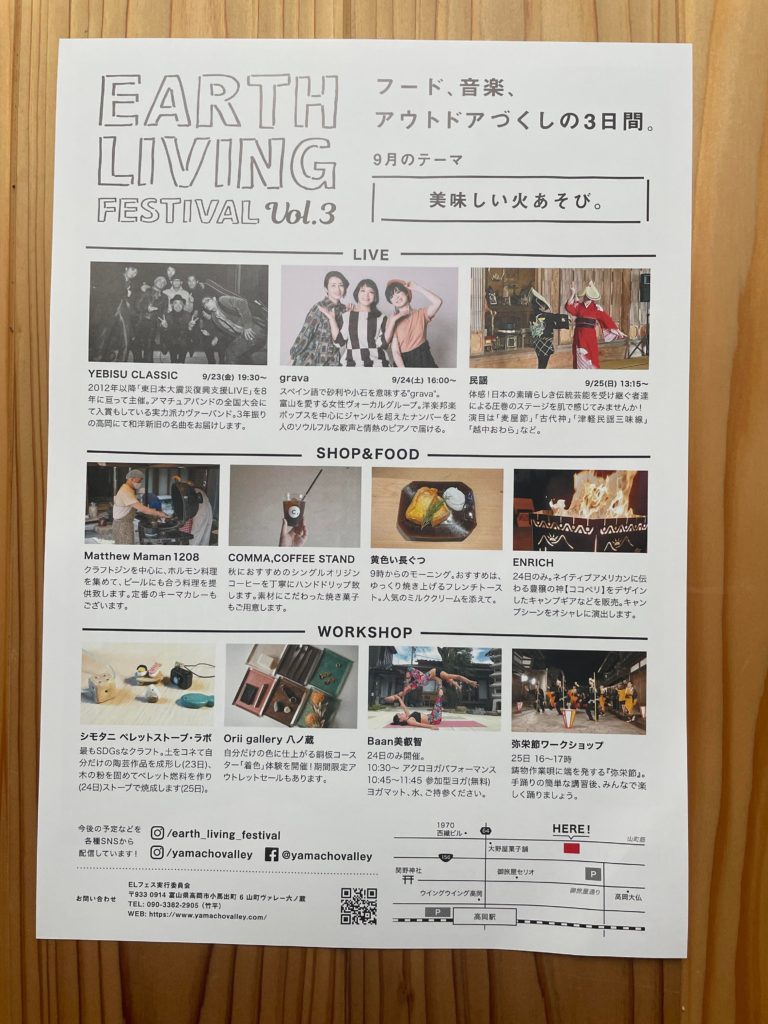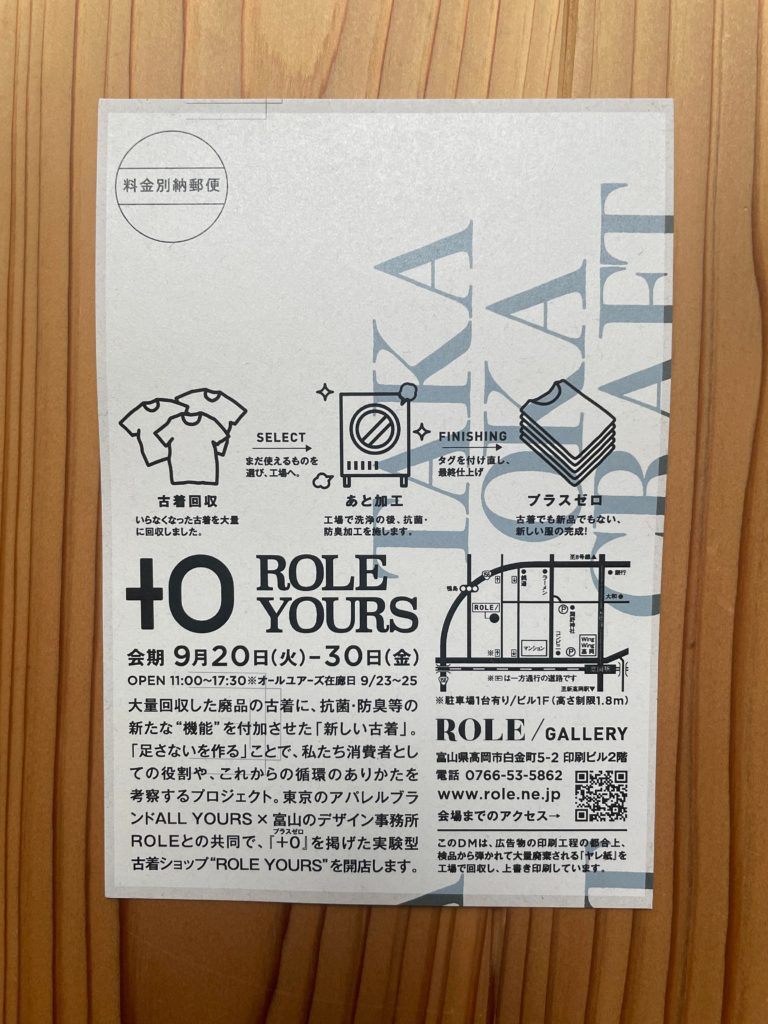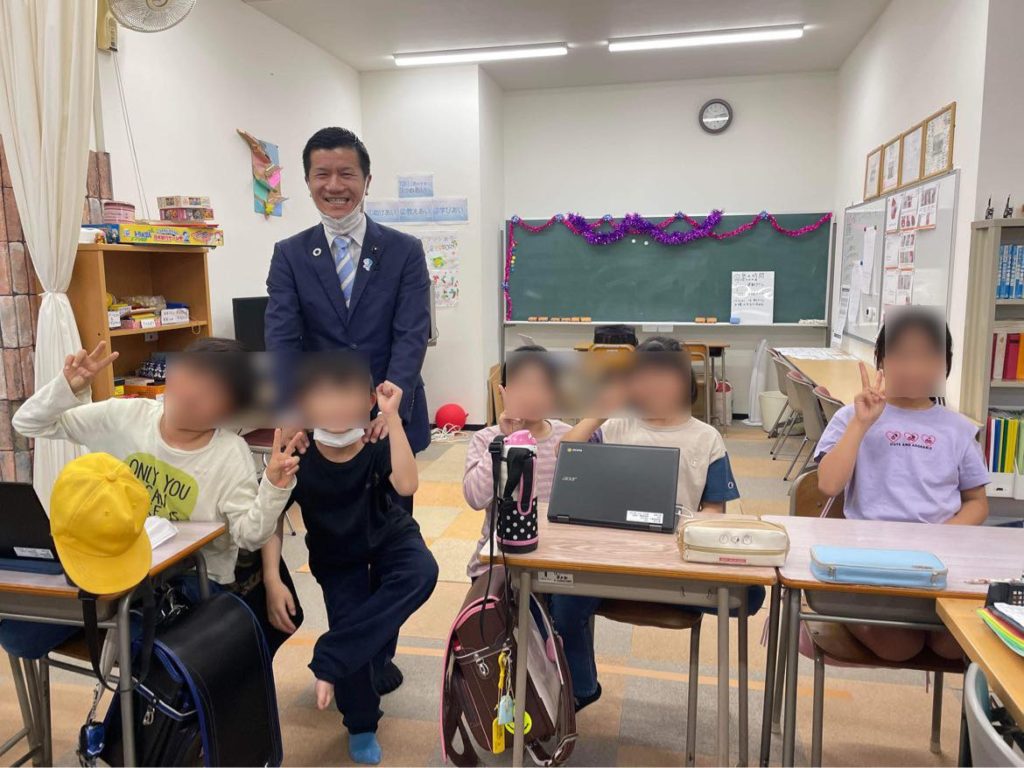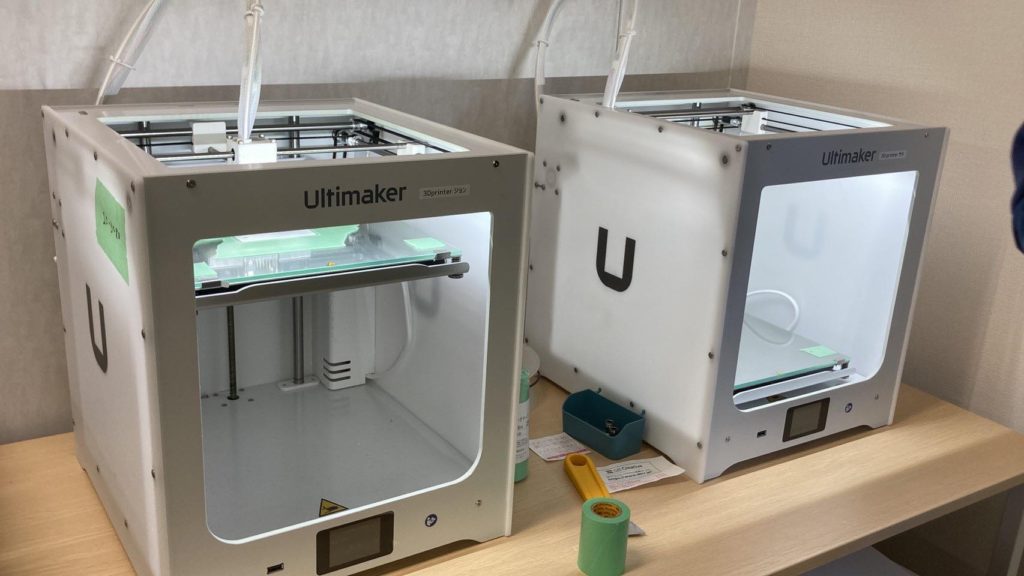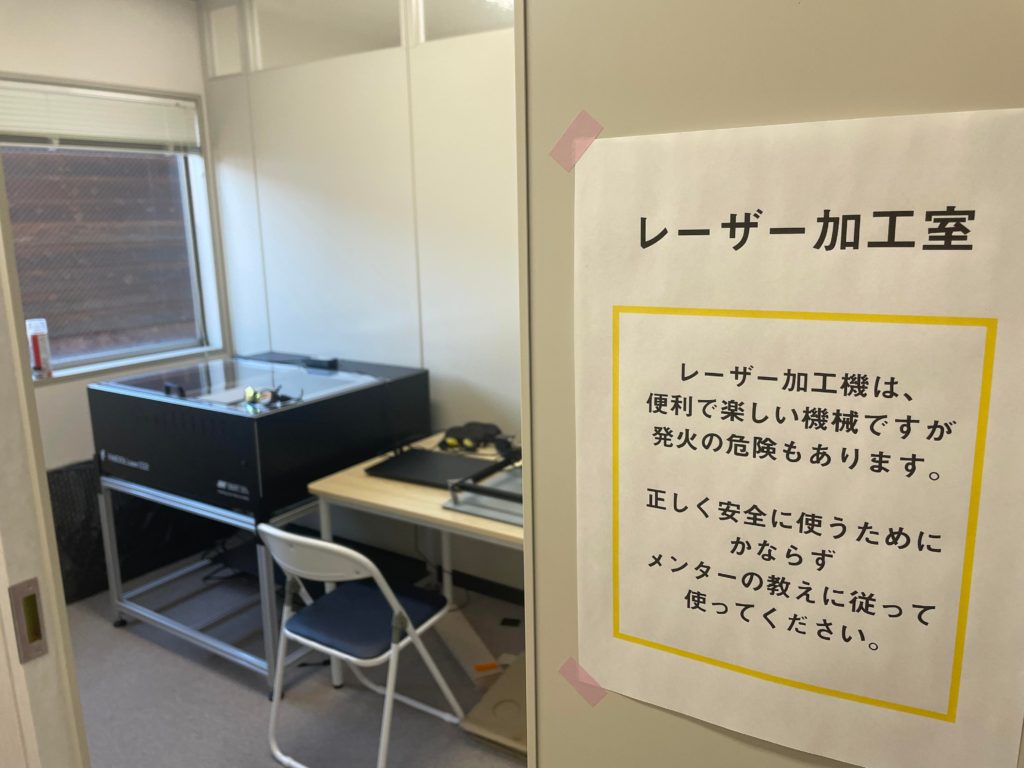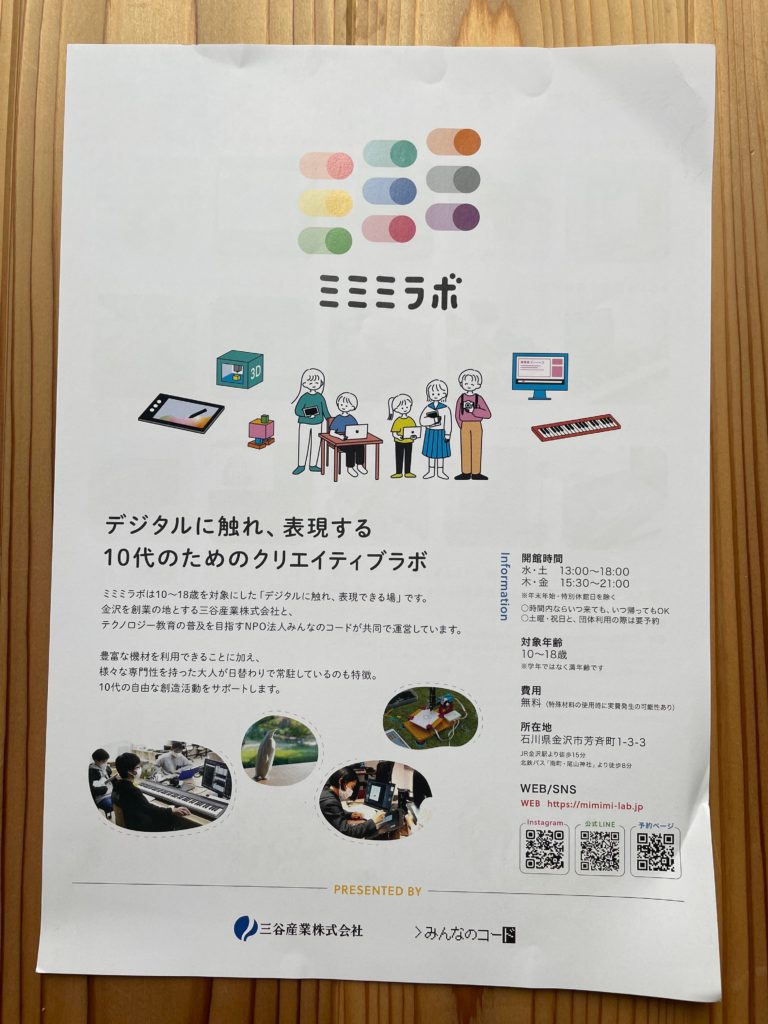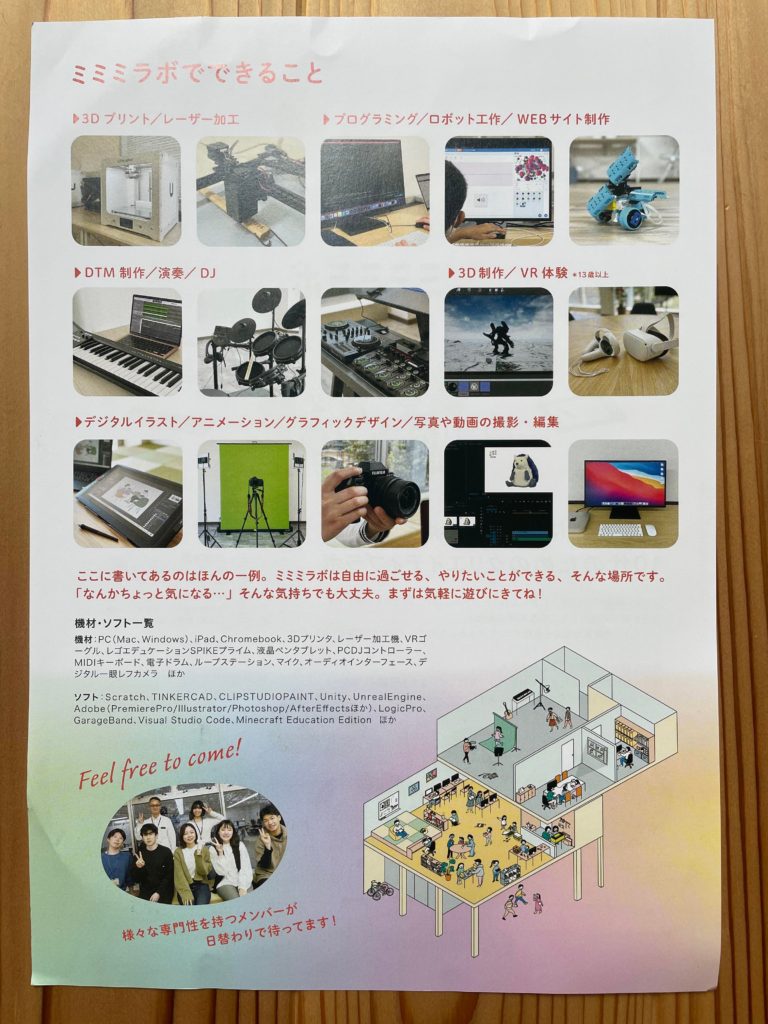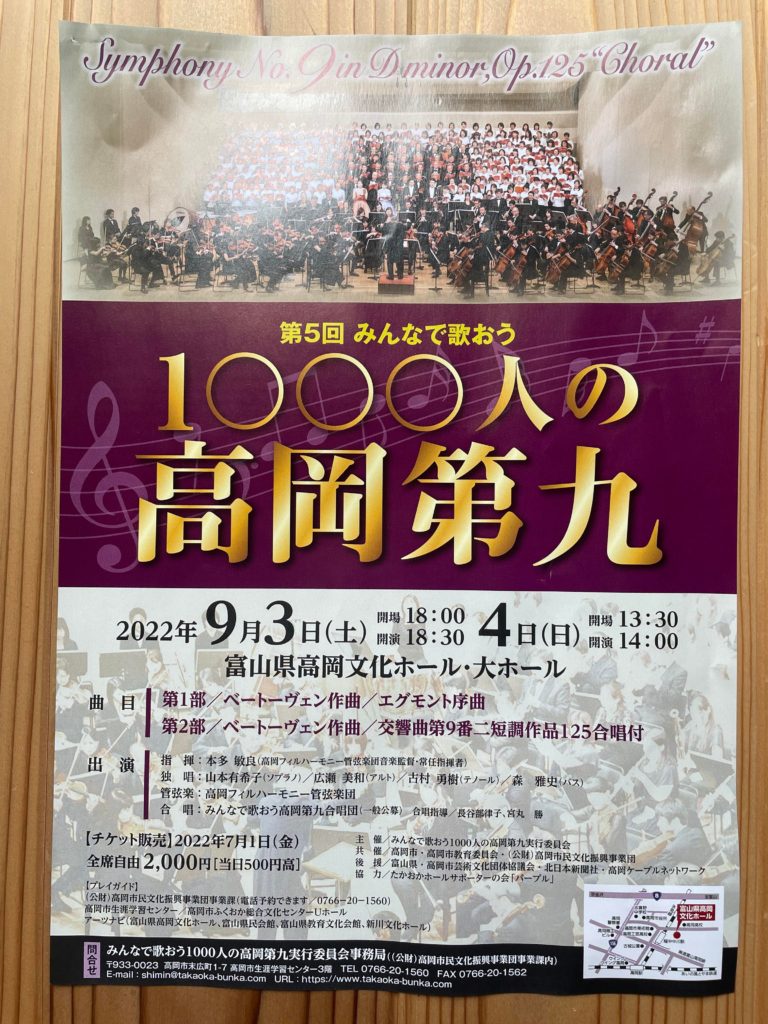こんにちは、富山県議会議員の瀬川侑希です。
–
市議会議員時代から続けていることですが、今年も政務活動費の使い道をご報告致します。
富山県議会のHPでも見ることはできますが、毎年自主的に公開したいと思っております。
–
以下、簡単にまとめさせて頂きます。すべて、会派とは別に個人で使用した分です。領収書を含む詳細は、富山県議会のHPにアップされています。
–
資料購入費:104,405円
新聞・雑誌:88,620円
「北日本新聞」3,380円×12ヶ月
「富山新聞」3,380円×12ヶ月
「富山県人」625円×12ヶ月
書籍:15,785円
「進化思考」3,300円
「DX最前線」1,210円
「わが列車わが鉄路」1,650円
「小学生からのSDGs」1,650円
「SDGsでつくるわたしたちの未来」1,155円
「d design travel 富山2」3,190円
「エコビレッジ そしてSDGs」1,650円
「子どもが面白がる学校を創る」1,980円
事務費:54,720円
携帯電話が劣化し、購入費の半額です(4年間で1度のみ半額申請できます)。
広聴広報費:1,514,086円
議会質問撮影代:13,200円
県政報告第2弾:印刷費451,000円+折込費84,858円+配達費665,028円
県政報告第3弾:デザイン費300,000円
調査研究費:132,090円
詳細は、富山県議会のHPにアップされています。
福井 LRT視察(えちぜん鉄道・福井鉄道):16,400円(車両費9,620円、有料道6,480円、駐車場300円)
岐阜 パークPFIなど視察(中之島公園など):30,280円(車両費13,320円、有料道6,070円、宿泊料10,890円)
立山 カルデラ砂防施設視察:12,800円(貸切バス12,800円)
岐阜 リサイクル工場など視察(エフピコなど):31,540円(車両費14,800円、有料道10,640円、宿泊料6,100円)
神奈川 デザイン思考を取り入れた行政の課題解決について意見交換(NOSIGNER):41,070円(鉄道28,970円、宿泊料12,100円)
研修費:45,000円
勉強会講師への謝礼(ハーチ株式会社CEO加藤佑さま 題:サーキュラーエコノミー(自治体との事例を中心に)):30,000円
webセミナーへの参加費(&Climate):10,000円
webセミナーへの参加費(アフターコロナの連携政策):5,000円
–
以上になります。
–
合計で1,850,301円の使用でした。
–
議員報酬もそうですが、政務活動費は税金です。その認識を決して忘れず、大切に使用していきたいと思います。これからも公開は続けていきます。